初めて自作PCを組む方などを対象として、マザーボードの選び方について解説していきたいと思います。
PCを組み立てる時に、全ての部品を取り付ける重要なマザーボードですが、どんなことに気を付けて選んだらいいのか分かりやすくご説明していきたいと思います。
マザーボードとは
マザーボードは、CPUやメモリーなどのパーツを取り付けるための基板です。マザーボードによって接続できるパーツが異なるので、PCの性能を決めるうえで重要なものがマザーボードということになります。
フォームファクター(サイズ)
マザーボードには、サイズが3種類あります。
それが、以下の3種類です。
上から下に向かってサイズが小さくなっていきます。
①ATX
②MicroATX
③Mini-ITX
各フォームファクター(サイズ)のメリット・デメリット
ATX
基盤が大きいため、拡張性で選ぶなら迷わずこれを選びましょう。
自作した場合、メモリやグラボなど色々と後から追加・変更をしたくなることが結構あると思います。
メモリで言えば、4つのスロットが一般的ですが、これが、MicroATXなどになってくると2つしかスロットがない製品もあります。
また、ケースに収めて、ケーブル類を取り回したりする時にも、作業スペースが広いのでケーブルやパーツの取り付けが楽です。
このように、メリットの一番の理由は、サイズが大きいことによる拡張性と作業性の高さです。
大きいのがメリットであり、最大のデメリットでもあります。
ATXのマザーボードを使用する場合、ケースも大きくしないといけないので、コンパクトにスッキリPCを設置したいという方には向きません。コンパクトを求めるなら、MicroATX以下を選びましょう。
ATXを机の上に置くと圧迫感がすごいので、人それぞれだと思いますが、足元が定位置になるのではないでしょうか。
MicroATX
ATXとMini ITXの中間にあたるので、大きすぎず、小さすぎない丁度良い大きさを考えるなら、MicroATXがいいのではないかと思います。
コンパクトになったことで、ATXに比べ設置スペースが小さくなるので、ケースにもよりますが机の上に置くことも可能になってきます。
小さくなることによって注意が必要な個所が増えます。
以下が注意が必要な個所になります。
- メモリスロットの数
- ビデオカードのサイズ
- 拡張スロットの数
このサイズだと、ケーブルの取り回しが、場所によって大変になります。
Mini-ITX
この規格の最大のメリットは、とにかくコンパクトなことです。
小さいが正義という方は、迷わずこれになるでしょう。
しかし、とにかく小さいために拡張性は捨てることになるので、拡張しないことを前提に組み立てるのがよいと思います。
小さいのは、とてもいいことなんですが、後々、性能面を強化していきたいと考えている場合には、Mini-ITXはおすすめしません。
- メモリが2スロット
- 拡張スロットが1スロット
- ビデオカードのサイズ
CPUソケット
PCの性能の根幹となるのがCPUになるので、まずは、使用するCPUを決めましょう。
メーカーは、Intel・AMDのどちらかになります。
CPUが決まらないと、マザーボードが決まりませんので、まずは、どのくらいの性能で組んでいくか決めておくことが必要でしょう。
CPUを載せる部分のことをCPUソケットといいます。
CPU側のソケット形状とマザーボード側のソケット形状が同じでなければ装着できません。
ソケット形状は、IntelとAMDで違いますし、同じメーカーでもCPUの各世代によってもソケット形状が異なります。
例えば、Intelの第11世代のCore iシリーズ(ソケット形状:LGA1200)を、第12世代用マザーボード(ソケット形状:LGA1700)に装着することはできません。そのため、購入前に、「CPU側のソケット形状とマザーボード側のソケット形状が同じかどうか」をしっかり確認しましょう。
また、LGA1151という名称でも、バージョンが異なっていたりして使用できないこともあるのでよく確認しましょう。
初めてPCを組む方におすすめCPU
今だとIntelであれば、最新CPUは、Core iシリーズのCPUは12世代なります。
みなさんも、Core i3・i5・i7・i9などというのを聞いたことがあると思います。
その他に、celeronなどの格安CPUもありますが、コスパ重視で選ぶならありですが、ストレスなくPCを使用したいなら、Coreiシリーズをおすすめします。
最新のCPUが性能的に一番いいのは当然ですが、新しい物は高いということにもなるので、コスパを狙って9世代を選択していくのがいいと思います。1世代前のCPUでも十分高機能なので、全く問題ありません。
選ぶ基準としては、動画編集やゲームなどをしていくなら、i7・i9をおすすめします。
ネットや動画程度を見るくらいで考えているなら、i5程度でもいいかもしれませんね。コスパはかなりいいです。ただし、少し長く使用することを考えるなら、Core i7以上をおすすめします。

CPUと密接な関係にあるチップセット
CPUと密接な関係にあり、とても重要なパーツになります。
Z690やH670などマザーボードの製品名になるくらいチップセットはとても重要です。
このチップセットによって、対応するCPUが異なったり、メモリの枚数や最大容量、USB端子の数など拡張性や性能面が大きく変わってくるので、使用したいCPUが使用できるかなどしっかりチェックしましょう。

メモリースロット
メモリースロットは、出来れば4本搭載できるATX又はMicroATXがおすすめです。
自作PCは、金銭的に頻繁に組み立てられるものではないので、増設の可能性が高いメモリが4本搭載できるものを選択しておきたいところです。
コンパクトなPCが最優先なら2スロットという選択肢になるでしょう。
メモリの購入の際は、こちらを参考にして下さい。

M.2ソケット
最近ですと、OSを入れるのは、M.2が主流になっていると思います。
速度が、SATA SSDと比べると3~10倍くらい違うので、予算に余裕がある方は、M.2の使用をおすすめします。M.2ソケットは、1つあれば問題ないと思います。
ATXなら2ソケットあることが多いです。
出来れば、M.2は発熱がすごいので、ヒートシンクがあるものを選んでおくのがよいと思います。
また、M.2には、SATA接続のものと、NVMe接続のもとのがありますので、このあたりもチェックしておくといいと思います。
M.2 SSDとは

M.2のSATAやNVMeについてはこちらをご覧下さい。

SATAポートの数
SSDやHDDを搭載するためのポートです。ポートの数は、自分が搭載しようとしているSSDなどの数を事前に決めておくことをおすすめします。
RAIDを構成しようと考えているなら、ここの数は、多いほどいいと思います。
SATA SSDとは


IOパネル(バックパネル)
PCの裏側にある、様々なコネクタを挿す部分です。
自分に必要なコネクタを考えておきましょう!

最近のモニターなら「DisplayPort」「HDMI」があれば問題ないでしょう。
数年前のモニターだとDVI-Dなどの端子がある製品もありますが、あえて使用する端子ではないので、HDMIかDisplayportを使用するのがよいでしょう。
ビデオカードを考えている場合には、ビデオカードの端子も確認しましょう。
- HDMI
- Displayport
- DVI-D
現在主流は、1Gbps対応で問題ありませんが、将来的なことを考えると、2.5Gbps以上対応の端子があるといいかもしれません。
ただ、ATXやMiroATXを選択する場合には、必要になった時にNIC(LANカード)を増設出来るので、そこまで気にしなくていいと思います。
端子の数と規格を確認しておきましょう。
USB3.0や3.1など速度が異なるので、出来るだけ転送速度の速い端子が多い製品を選ぶといいと思います。

拡張スロット(PCI-E、PCIスロットなどと呼ぶことも)
ビデオカードや様々な拡張カードを接続するためのスロットです。
大きいビデオカードなどを挿すことを考えているなら、スロット数が多い製品を選んでおきましょう。
ビデオカードは、2スロット消費してしまうので、この辺も考慮しておきましょう。
ビデオカード以外だとNIC(ネットワークカード)、M.2 SSD拡張カードなどが考えられると思います。
- サウンドカード
- USB増設カード
- NIC(LANカード)
- キャプチャーボード
- WiFi(無線LAN)カード

主なマザーボードのメーカー
現在、以下のメーカーのマザーボードを選んでおけば問題ないでしょう。
[2022 自作PC] マザーボードの失敗しない選び方! チェックしよう!まとめ
マザーボードを購入するうえで、気を付けたい点を、各パーツごとにご説明しました。
PCというのは、日進月歩ですぐに性能のいいパーツが登場していきますので、出来るだけ長く使用したい場合には、現時点で最新のパーツが搭載できるマザーボードを選んでおくことをおすすめします。
頻繁に自作する場合には、コスパ重視でもいいですが、後悔のないようパーツ選べびには時間をかけて下さい!

















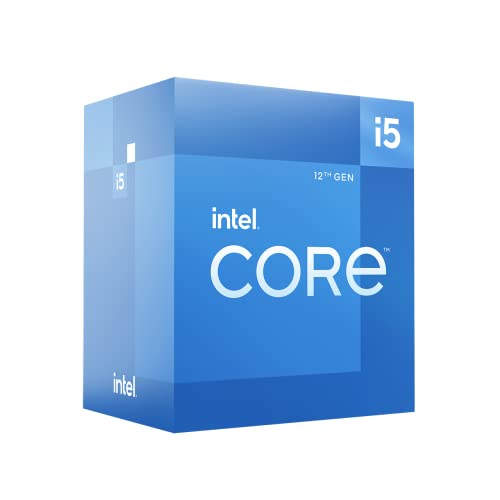



























![MSI MPG Z690 CARBON WIFI マザーボード ATX [Intel Z690チップセット搭載] MB5600](https://m.media-amazon.com/images/I/41ZXFA3+PPL._SL160_.jpg)









![MSI MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4 マザーボード ATX [Intel H670チップセット搭載] MB5704 ブラック](https://m.media-amazon.com/images/I/41Sy7-ul80L._SL160_.jpg)

















![GIGABYTE Z690 AERO G Rev. 1.0 マザーボード ATX [Intel Z690チップセット搭載] MB5573 ホワイト](https://m.media-amazon.com/images/I/41tnuvHS5TL._SL160_.jpg)




コメント